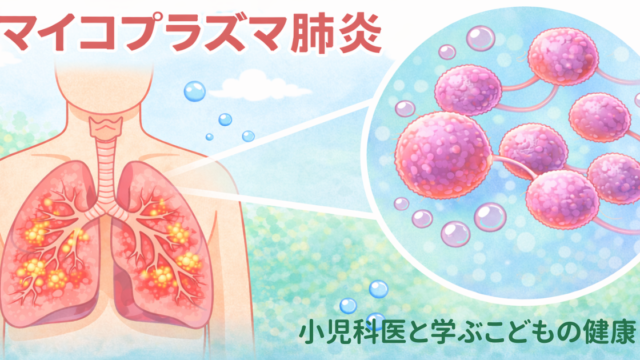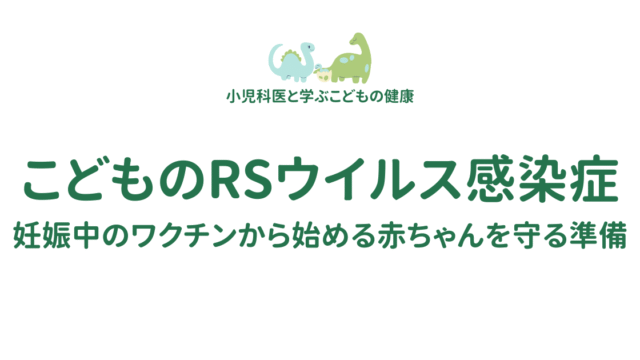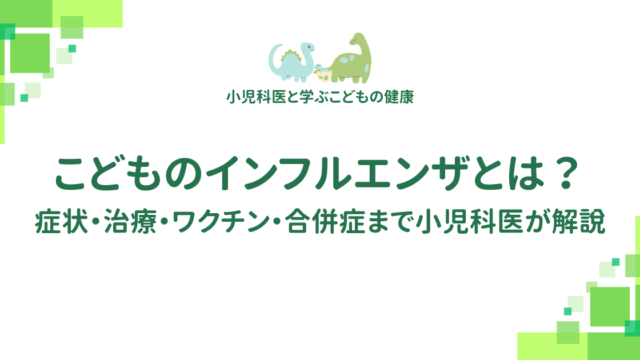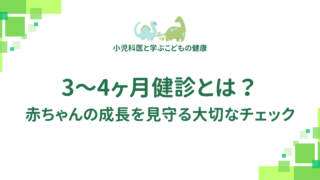こどもが突然高い熱を出したり、のどを痛がったりすると、とても心配になると思います。
その原因の1つが「溶連菌感染症」です。
この記事では、溶連菌感染症の症状や合併症、治療のポイントについて、小児科医としてわかりやすく解説します。
この記事では、溶連菌が喉に感染した「溶連菌性咽頭炎」について解説します。
溶連菌とは?

溶連菌とは喉や皮膚や首のリンパ節など様々な場所に感染する細菌です。
今回の記事では、「溶連菌性咽頭炎」についてみていきます。
5〜15歳のこどもに多く、小学生に多いです。
日常の咳やくしゃみなどで周囲に感染し、学校などで流行します。
咽頭炎の原因のうち 15〜30%が溶連菌によるもので、ほかはほとんどウイルス性です。
溶連菌性咽頭炎は抗菌薬(抗生物質)が効く唯一の咽頭炎です。
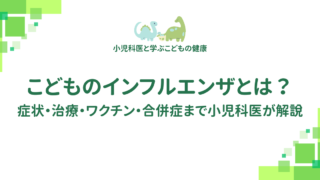
溶連菌性咽頭炎の主な症状

- 38℃以上の発熱
- 強いのどの痛み
- 扁桃腺や首のリンパ節の腫れ
- 咳や鼻水が目立たない
- 舌が赤くぶつぶつする「いちご舌」
- 頭痛、腹痛、吐き気
「熱が高いのに咳や鼻水が少なく、のどが強く痛い」時には、溶連菌を疑います。
溶連菌性咽頭炎の合併症

溶連菌に感染すると、以下の合併症を引き起こすことがあります。
溶連菌感染後急性糸球体腎炎
溶連菌感染から1〜2週間後に発症します。
尿に血液やタンパクが混じる、顔のむくみ、尿が少ない、血圧が高いという症状がでます。
高血圧があると脳症のリスクがあるため、入院での血圧管理や適切な治療が必要となります。
リウマチ熱
溶連菌感染から2〜3週間後に発症します。
関節炎、心臓の弁膜症や心膜炎、皮膚症状や神経症状が出現します。
心臓の合併症の程度によっては、心不全に至ることもある怖い病気です。
繰り返し発症すると、心臓の合併症が悪くなっていくため、年単位の抗菌薬(抗生物質)の内服が必要になります。
そのほかの合併症
- 扁桃周囲膿瘍:のどの奥に膿がたまる首の重篤な感染症を起こす病気
- 劇症型溶血性レンサ球菌感染症:全身の臓器障害に陥る病気
- PANDAS:溶連菌感染をきっかけに精神・神経症状が出現する病気
どれもとてもまれな病気ですが、もし起こると心配な病気です。
溶連菌感染症に早めに気づき適切に治療を受けることが大切です。
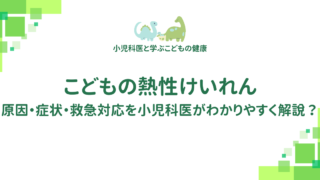
溶連菌性咽頭炎の検査と診断

咽頭の所見や発熱がある場合に、迅速抗原検査を行います。
12〜20%のこどもは溶連菌を「保菌」しているため、症状がある場合のみ検査します。
保菌とは、喉に溶連菌はいるけど、感染はしていない状態です。
保菌だけであれば、治療は必要ありません。
溶連菌性咽頭炎の治療

適切な抗菌薬を10日間
きちんと飲み切ることが大切です。
抗菌薬を飲むと、すぐ熱が下がり、喉の痛みも引きます。
それでも合併症の予防のために10日間の抗菌薬を飲み切ることが非常に大事です。
抗菌薬開始から24時間以内に解熱することが多いですが、それ以上熱が続く場合は再受診をおすすめします(川崎病など他の似た症状が出る病気の可能性があります)。
川崎病については次の記事をご覧ください。

ご家庭での工夫

のどが痛いときは、熱いもの、辛いもの、酸っぱいものは避けましょう。
食事がつらいときは、ゼリーなど飲み込みやすいものがおすすめです。
抗菌薬を開始するとすぐ良くなりますが、つらい時は解熱薬を使用してあげましょう。
抗菌薬は周囲に感染させないために大切です。
よくある質問(Q&A)

Q1. 兄弟や家族にうつりますか?
はい。物を共有せず、咳やくしゃみのエチケットを守りましょう。家族内で高熱やのどの痛みが出たら、早めに受診しましょう。
Q2. 薬は元気になったらやめてもいいですか?
薬を途中でやめると合併症のリスクが高まります。10日間飲み切ることが大切です。
Q3. 学校や園は何日休む必要がありますか?
適切な抗菌薬を飲み始めてから24時間経ち、解熱していれば、登校・登園可能です。
発熱など体調に応じて調整しましょう。
まとめ(Take Home Message)

「高熱+のどの強い痛み」は溶連菌が疑われます。
溶連菌と診断されたら抗菌薬を10日間飲み切ることが大切です。

あとがき
溶連菌感染症は珍しい病気ではなく、多くのこどもがかかる身近な感染症です。
しかし、正しく治療しなければ合併症を発症することがあります。ご家庭での観察と医師の指示に沿った治療がとても大切です。
この記事が少しでも保護者の皆さまの安心につながれば幸いです。
※本記事は、一般的な医療情報を提供することを目的としており、診断や治療を行うものではありません。
お子さまの症状や体調について不安がある場合は、必ず医療機関を受診し、医師の診察を受けてください。
山田健太著. 笠井正志・伊藤健太監修. 小児感染症のトリセツ2025疾患編. 金原出版; 2025
岡本充宏. 小児科ですぐに戦えるホコとタテ. 診断と治療社. 2022
リウマチ熱 – 19. 小児科 – MSDマニュアル プロフェッショナル版
最後までお読みいただきありがとうございます。
このブログでは「こどもの病気や健康」に関する正しい情報を小児科医の視点からお届けしています。
他の記事もぜひチェックして、日々の子育てにお役立てください。