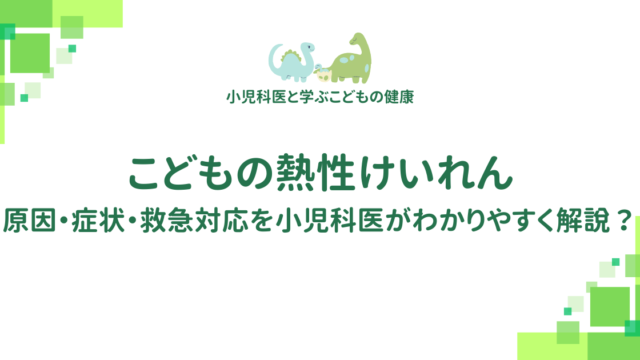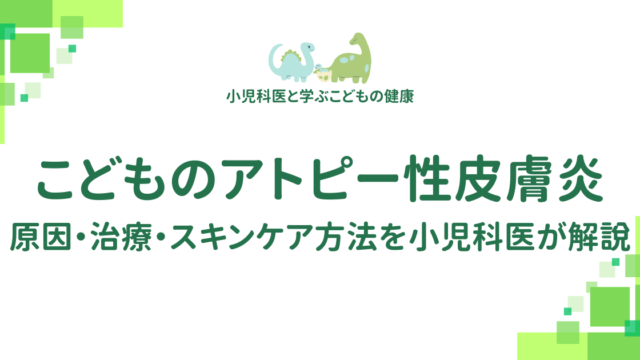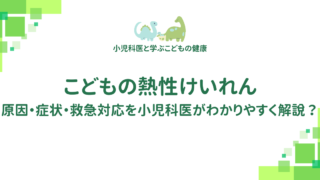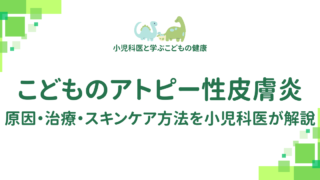こどもが高熱や発疹を出すと、「本当にただの風邪かな?」と心配になりますよね。
その中でも、実際にかかって初めて知る方が多い病気のひとつが「川崎病」です。
川崎病は、心臓に後遺症を残す可能性のある病気です。そうならないためにも、保護者の方が正しい知識を持ち、早めに診断につなげることがとても大切です。
この記事では、川崎病の症状・診断・治療・退院後の生活について、小児科医として分かりやすく解説していきます。
川崎病とは?

川崎病の特徴
- 4歳以下の乳幼児に多いが、学童期以降の発症することもある。
- 日本では70人に1人の頻度で発症する。
- 東アジアのこどもに多い。
- 原因はまだ判明していない。
川崎病はあまり一般的には知られていませんが、日本で意外とよく遭遇する病気です。
川崎病を初めて知った保護者の方がほとんどです。
この記事で一緒に学びましょう!
川崎病の合併症|冠動脈瘤とは?
川崎病は全身の血管に炎症が起こる病気です。
心臓を栄養する血管である冠動脈に炎症が及ぶこともあります。
それにより起こる合併症が冠動脈瘤です。
冠動脈瘤ができると、将来的に狭心症や心筋梗塞といった心臓の病気のリスクが高まります。
川崎病では、「冠動脈瘤」を残さないことが何よりも大切です。
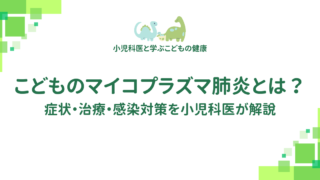
川崎病の症状と診断基準

- 高熱がつづく
- 目が赤くなる
- 唇・舌・口の中が赤くなる
- 発疹が出る
- 手足の指先が赤く腫れる
- 首のリンパ節が腫れる
上記の症状のうち5つ以上を満たすと「川崎病」と診断されます。
5つ以上の症状がそろわない場合でも「不全型川崎病」と診断されることがあります。
川崎病は、「こどものからだが全体的に赤くなる病気」と覚えておきましょう。
発症してすぐは症状が揃わず、診断が難しいことがあります。
川崎病を念頭に置いて症状を観察することが重要です。
川崎病とよく似た症状の病気として、溶連菌感染症やアデノウイルス感染症などがあります。
いずれも発熱や首の腫れ、のどの症状があり、川崎病と区別がつきにくいことがあります。
詳しくは以下の記事を参照してください。

川崎病の治療法|入院・点滴・薬の流れ

川崎病は、入院して免疫グロブリン療法とアスピリン内服で治療します。
川崎病の治療の目標は、「冠動脈瘤を残さないこと」です。
高熱が10日間以上続くと冠動脈瘤ができやすくなります。
できるだけ早く川崎病と診断して、早く治療を始めることが後遺症を防ぐ鍵になります。
免疫グロブリン療法
現在、川崎病の治療で最も世界的に標準とされているのが「免疫グロブリン療法」です。
この治療により、強い炎症を速やかに抑え、冠動脈瘤の形成を防ぐ効果があります。
免疫グロブリン療法
- 細菌やウイルスからからだを守ってくれる抗体が本体です。
- 1〜2日間かけて点滴投与します。
- 80%以上がこの治療で改善します。
IVIGの副作用として、まれにアレルギー反応や一時的な血圧の低下などがあります。
ただし、医療スタッフがしっかり管理しながら治療を行うため、安全に投与できます。
免疫グロブリンを点滴しても熱が下がらない場合には、再投与することがあります。
アスピリン
「アスピリン」はバファリンにも含まれている飲み薬です。
炎症を抑える働きに加えて、血液をサラサラにして血のかたまり(血栓)を予防する働きもあります。
川崎病の治療では心臓の血管に合併症が残らないように使われています。
アスピリン
- 発熱中:1日3回に分けて内服し、炎症をしっかり抑えます。
- 解熱後:1日1回の内服に減らし、「心臓の血管に「冠動脈瘤」の予防目的」で、2〜3か月ほど続けます。
アスピリン服用中にインフルエンザや水疱瘡にかかると、「ライ症候群」と呼ばれる重篤な急性脳症を引き起こすことがあります。
感染症にかかった場合は必ず医師に相談しましょう。
その他の治療
以下のガイドラインに沿って、治療は行われます。詳しい他の治療については参照してください。
日本小児循環器学会 川崎病急性期治療のガイドライン(2020年改訂版)
入院期間
順調に回復すれば1週間ほどで退院できることもあります。
発熱が長引くとその分だけ長くなります。
川崎病治療後の生活

退院後の内服
冠動脈瘤の予防目的として、退院後もアスピリンを飲み続けることが必要です。
発症から2〜3か月間内服を続け、心臓超音波検査で冠動脈に異常がなければ内服を終了できます。
川崎病治療後の生活や運動制限
冠動脈に後遺症が残らなければ、普段通りの生活や運動が可能です。
ただし、発症から5年間は定期的に心臓超音波検査を受けて、冠動脈瘤ができていないかを確認していくことが大切です。
ワクチン接種の注意点
川崎病の治療で免疫グロブリン製剤を使用した場合、その影響で皮下注射の生ワクチン(MRワクチン、水痘ワクチンなど)の効果が弱くなります。
そのため、皮下注射の生ワクチンの接種は6か月間控える必要があります。
予防接種のスケジュールは、お子さんの治療経過や年齢によって調整が必要になるため、必ず主治医の小児科で相談してください。
まとめ(Take Home Message)
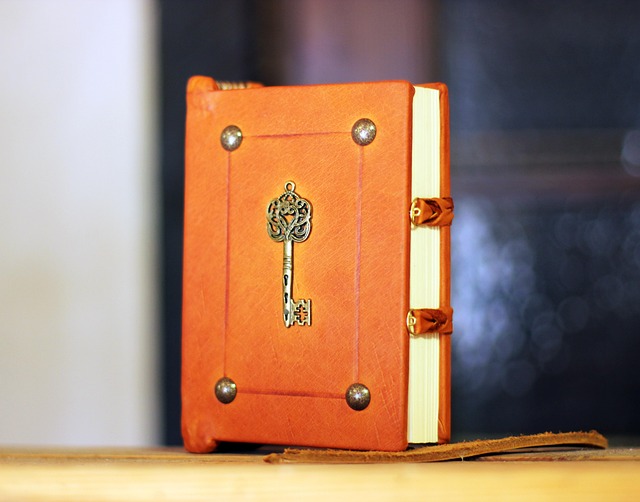
川崎病は早期診断・早期治療が重要な病気です。川崎病を疑う症状があれば、すぐに小児科へ!
入院で点滴と内服で治療します。
ほとんどのこどもが後遺症なく回復できますが、冠動脈瘤には注意が必要です。
ワクチンのスケジュールには注意が必要です。
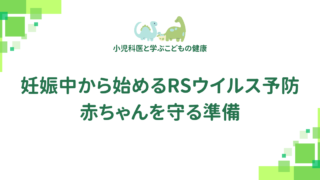
あとがき
川崎病は聞き慣れない病気ですが、早期に適切な治療を受ければ、こどもが元気に回復できる病気です。
この記事が、川崎病を初めて知った保護者の方にとって少しでも安心につながれば嬉しく思います。
川崎病心臓血管後遺症の診断と治療に関するガイドライン(2020年改訂版)
日本小児循環器学会 川崎病急性期治療のガイドライン(2020年改訂版)
岡本 充宏. 小児科ですぐに戦えるホコとタテ. 診断と治療社, 2022年
最後までお読みいただきありがとうございます。
このブログでは「こどもの病気や健康」に関する正しい情報を小児科医の視点からお届けしています。
他の記事もぜひチェックして、日々の子育てにお役立てください。