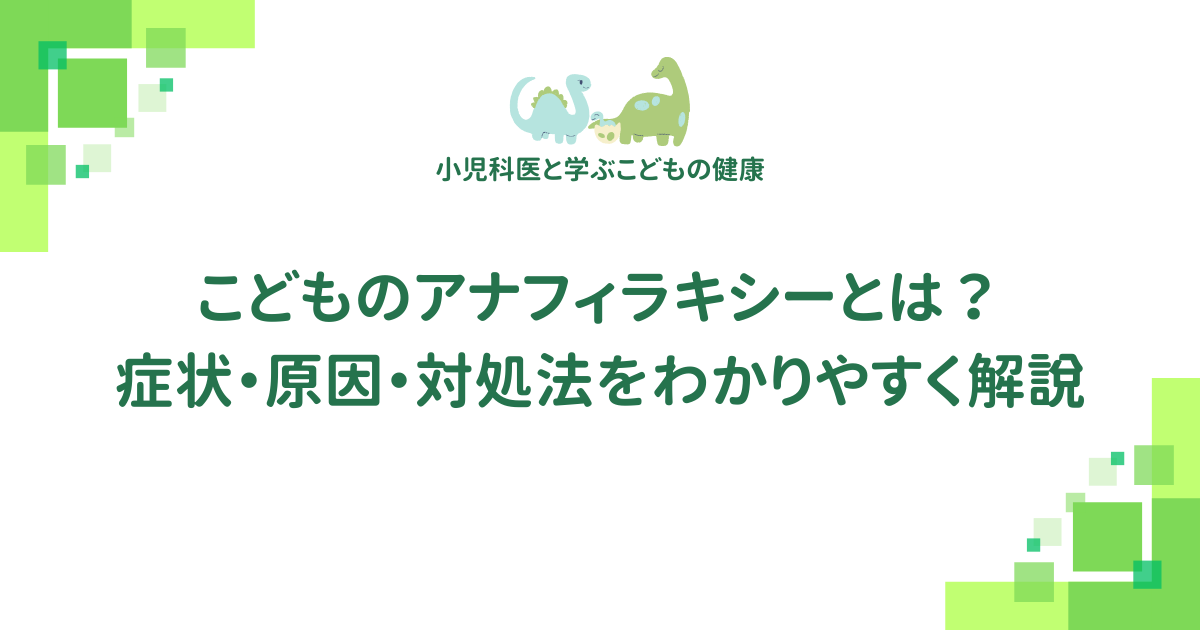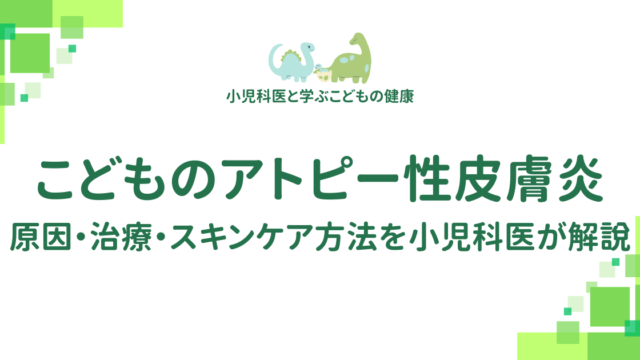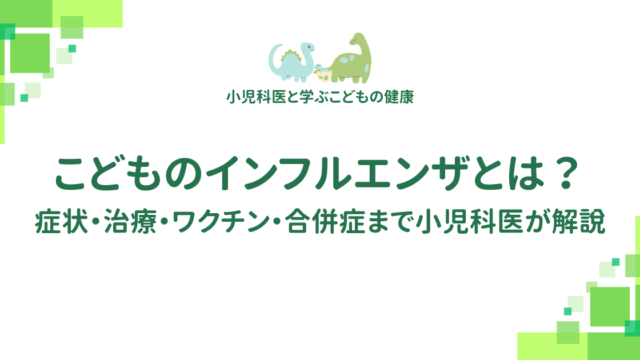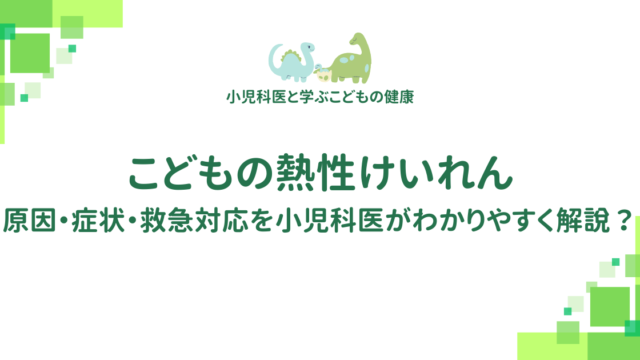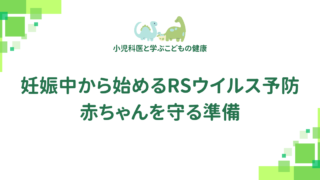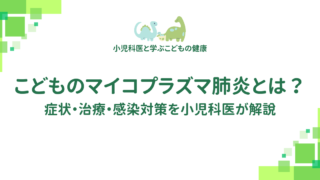こどもが突然、息苦しそうになったり、全身に蕁麻疹が出たりしたら…。それが「アナフィラキシー」かもしれません。
アナフィラキシーは、アレルギーの中でも命にかかわる重篤な反応です。
しかし、正しい知識と準備があれば、いざという時に慌てずに対応できます。
この記事では、アナフィラキシーとは何か、子どもに起きたときの症状や原因、すぐにできる対応法、再発予防まで医師がわかりやすく解説します。
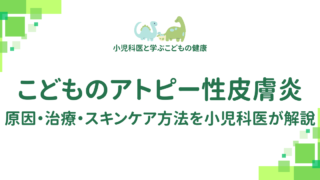
アナフィラキシーとは?原因や発症の仕組み
アナフィラキシーとは、アレルゲン(アレルギーの原因物質)に触れた直後、全身に急激なアレルギー反応が起こる状態です。
皮膚・呼吸器・消化器・循環器など複数の臓器に症状が現れ、時に命に関わる状態に陥ることもあります。
こどもの場合、アレルゲンに初めて触れた後、短時間で発症することが多く、発見から数分~数十分で急速に悪化することもあるため、迅速な対応が求められます。
原因となるアレルゲン
こどもに多いアナフィラキシーの原因は、以下のようなものです。
- 食物アレルギー(最も多い)
- 卵、牛乳、小麦などの三大アレルゲン
- 近年増加中:木の実類(くるみ、カシューナッツ、ピーナッツなど)
- ハチの刺傷
- 薬剤(抗生物質・解熱鎮痛薬など)
- ラテックス(ゴム)
- 造影剤(検査で使用)
- 運動誘発性(食後の運動で起こるケースも)
特に近年、木の実アレルギーが増えており、重症化しやすいことがわかってきています。
離乳食やおやつに含まれるナッツ類には注意が必要です。
アナフィラキシーの症状とは
以下のように、2つ以上の臓器に症状が出る場合はアナフィラキシーを強く疑います。
皮膚・粘膜:じんましん、かゆみ、赤み、唇の腫れ
呼吸器:咳、ゼーゼー(喘鳴)、喉の違和感、息苦しさ
消化器:嘔吐、腹痛、下痢
循環器:ぐったりする、血圧低下、意識がぼんやりする
とくに「呼吸の異常」や「意識がもうろうとする」場合は、すぐに救急対応が必要です。
アナフィラキシーの正しい対応
- 迷わず救急車(119)を呼ぶ!
呼吸困難、ぐったりしている、意識が悪いなどの症状があれば迷わず通報。 - アドレナリン自己注射(エピペン)を使う
すでにアレルギーが分かっていて医師から処方されている場合、できるだけ早く打つことが命を救うカギです。
太ももの外側に、衣服の上からでもOK。 - 体の体勢は「あおむけ(仰臥位)」+ 足を30cmほど高く
足の下にまくらやクッションなどを入れてあげましょう。
嘔吐がある場合は横向きで。 - 到着するまで、呼吸・意識を観察
心肺停止に至ることはまれですが、観察を続けます。
アドレナリンって怖くないの?
アドレナリンは、命を救うための薬です。アナフィラキシーの治療として1番鍵となる治療です。
「副作用が心配」と思う方もいますが、アナフィラキシーによる命の危険と比べれば、使わないリスクの方がはるかに大きいとされています。
アドレナリンは正しく使用すれば安全で、効果は注射後すぐに現れます。
使うタイミングが遅れるほど、症状が重くなる可能性が高くなります。
アナフィラキシーの再発予防
- 原因アレルゲンの特定と除去
血液検査や食物負荷試験でアレルゲンを明らかにし、食事や生活から除去する工夫を。 - 保育園・学校と連携する
食事内容の確認、アレルギーカードの作成、エピペンの管理方法の共有など。 - 家族や周囲への情報共有
保護者だけでなく、祖父母や保育者にも対応方法を伝えることが重要です。
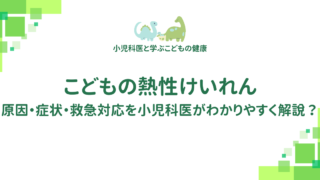
まとめ
アナフィラキシーは命に関わるアレルギー反応
食物(特に木の実類)が主な原因に
呼吸器・意識の異常は要注意!すぐに救急車とアドレナリン
怖がらずにエピペンを使うことで命が助かる
普段からの予防と連携が大切
あとがき
急なじんましんや息苦しさ、呼吸が止まりそうな感覚。アナフィラキシーの症状は、突然で本当に怖いものです。
でも、正しい知識と準備があれば、大切な命を守ることができます。
心配な方は、小児科やアレルギー専門医に相談し、一歩早い対策をしておきましょう。
家族全員で備えることが、こどもにとって最も安心できる環境になります。
日本アレルギー学会.アナフィラキシーガイドライン2022
厚生労働科学研究班.小児アレルギー疾患の診療の手引き2023
岡本充宏. 小児科ですぐに戦えるホコとタテ. 東京: 診断と治療社; 2022
最後までお読みいただきありがとうございます。
このブログでは「こどもの病気や健康」に関する正しい情報を小児科医の視点からお届けしています。
他の記事もぜひチェックして、日々の子育てにお役立てください。