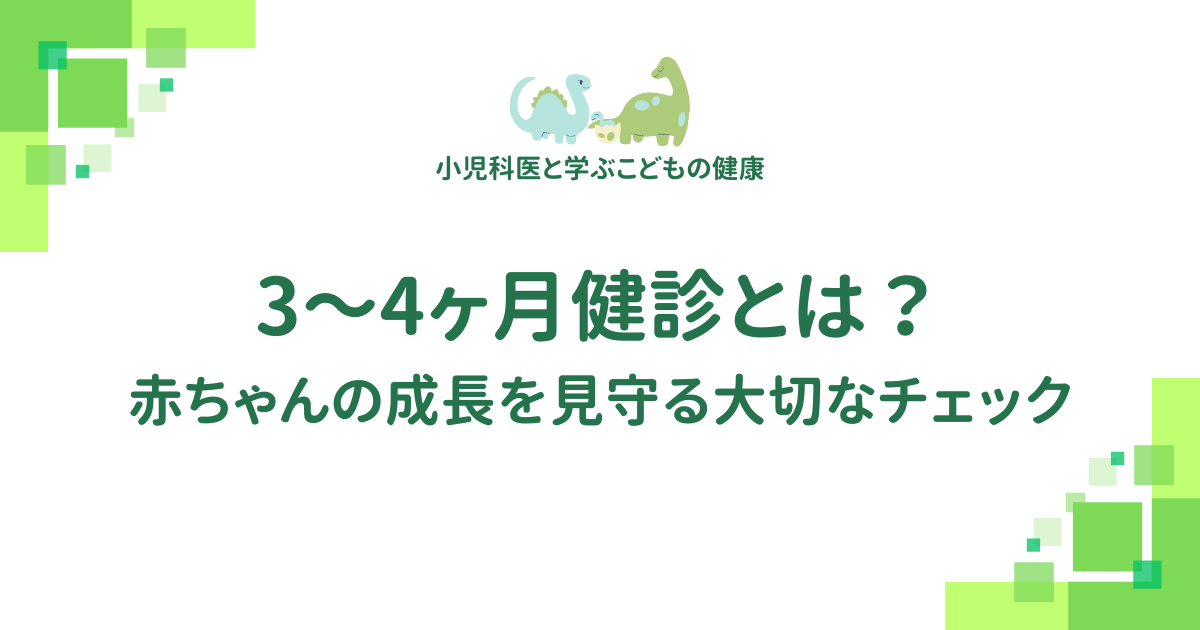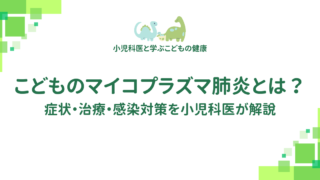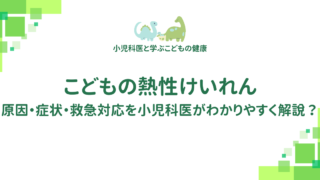赤ちゃんが生後3〜4ヶ月になると、「3〜4ヶ月健康診査」があります。
からだの「成長」だけでなく、首のすわりや反応など「発達」を確認する大事なタイミングです。
この記事では、3〜4ヶ月健診の内容や目的、よくある質問について、小児科医としてをやさしくまとめました。
3〜4ヶ月健診ってどんなもの?

多くの自治体ごとに3〜4ヶ月の月齢の赤ちゃんが集まる集団健診です。
主に、赤ちゃんの成長(身長・体重・頭囲)と発達(首すわり、腹這いなど)のチェックを行います。
目や耳、股関節、皮膚などの健康状態も確認します。
ご家族が日頃感じている不安や疑問を相談できる貴重な機会です。
この頃は、首がしっかりしてきたり、あやすと笑うようになったりと、成長や発達がぐんと進む時期です。
健診では「順調に大きくなれているか」「発達に遅れがないか」を医師や保健師が丁寧に確認します。
育児の相談や異常が見つかった時には医療機関への紹介などを行っています。
1ヶ月健診については、以下の記事をご覧ください。

3〜4ヶ月健診のチェック内容

身体測定と体重の増え方
首のすわり
体の使い方
目と耳のチェック
お肌のチェック
股関節の動き
コミュニケーション
身体測定と体重の増え方
- 身長・体重・頭囲を測定します
- 体重は、生後2ヶ月までは1日約30g、その後は1日約20g増えるのが目安です。
- 哺乳状況も合わせて確認します
生後1ヶ月の時よりは体重の増えは少なくなりますが、まだまだ大きくなる時期です。
現在の体重だけではなく、1ヶ月健診からの体重の増え方も重要です。
首のすわり(定頸)
- 生後4ヶ月ごろの発達の評価として重要なチェックポイントです
- 上体を少し(45°程度)起こしたときに、首がしっかりついてくるかを確認します
- 腹ばいで顔が上がるかも確認します
まだ完全に首がすわっていなくても、3〜4ヶ月前半なら1ヶ月後に追いつくことも多いので心配しすぎなくても大丈夫です。
体の使い方
- 足をバランスよく動かせているか
- 抱っこしたときに体を強く反らすか
→泣いている時はよくある反応ですが、泣いていないのに強く反り返る場合は医師へ相談が必要です
「筋肉の緊張が強すぎないか」、「脳の未熟性がないか」のチェックポイントになります。
目と耳のチェック
- 動くものを目で追えるか(追視)
- 斜視がないか
- 音がした方を向くか、驚く反応があるか
赤ちゃんが「聞こえているか」「見えているか」は、ことばや体の発達に直結する大切な要素です。
お肌のチェック
- 赤いあざ(血管腫)が大きくなっていないか
→まぶたや口の近くなど、生活に影響する場所なら早めに相談してください。 - 青いあざ(蒙古斑)の大きさや場所、濃さは消えそうなものか
- 乳児湿疹の状態
血管腫や蒙古斑は、「そのうち消えるから大丈夫」と放っておいていい場合もあれば、早めの対応が望ましい場合もあります。気になるあざがあるときは、健診で医師に相談してみると安心です。
湿疹については以下の記事をご覧ください。
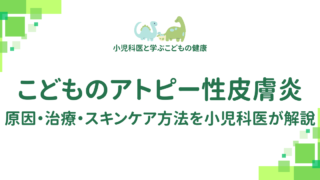
股関節の動き
- 股関節が左右同じように開くか
- 股関節を動かすと「コキッ」と音はしないか
- おしりや太もものしわに左右差がないか
これらの異常があると、発育性股関節形成不全(先天性股関節脱臼)の可能性があります。
放っておくと歩行困難や、治療期間の延長や負担の増加につながります。
疑った場合は、すみやかに整形外科に受診し、レントゲンで確認する必要があります。
コミュニケーション
- あやし笑いが出てきたか
- 声かけに反応するか
3〜4ヶ月ごろからはニコニコ笑ってくれる赤ちゃんが増えてきます。
3〜4ヶ月健診でよくある質問(Q&A)

Q1. 首がまだすわっていないけど大丈夫?
個人差が大きい時期です。3〜4ヶ月前半なら、1ヶ月後にはしっかりしてくることも多いです。1ヶ月経過しても首がすわらない場合は、医療機関での発達のフォローや必要に応じて精査が必要になります。
Q2. 頭の形(向き癖・絶壁)が気になります。
この時期によくある心配です。「日中に抱っこする」、「向きを変える」、「親の監視下で短時間うつ伏せ遊びを取り入れる」などで改善が期待できます。
Q3. 目が合いにくい、物を追わない気がします。
個人差がありますが、まったく追視がない、斜視が目立つときは相談してください。
Q4. 音に反応しないように見えます。
静かな環境でも反応が乏しいときは、聴力に問題があり、言葉の遅れにつながる可能性があるので、早めに受診がおすすめです。
Q5. 離乳食はいつ始めればいいのか?
日本では5~6ヶ月ごろからの開始が推奨されています。それよりも前の開始は栄養面的にもメリットが少ないです。
3〜4ヶ月健診を受けるメリット

健診を受けるメリットとして以下のようなことがあります。
専門家が赤ちゃんの成長・発達を見守ってくれる
病気や発達の遅れを早めに発見できる
授乳・睡眠・スキンケアなど育児相談ができる
予防接種のスケジュールを確認ができる
育児で溜まりに溜まった疑問点を解消できる
ここまで見てきたように、3〜4ヶ月健診で確認することはたくさんあります。
3~4ヶ月健診の次の検診は9~10ヶ月健診とかなり間隔が開くので、このタイミングで育児の心配事や疑問点は解消しておきましょう。
まとめ(Take Home Message)
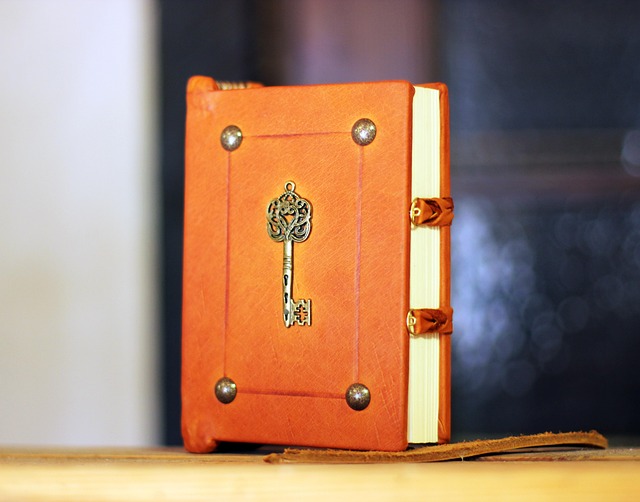
3〜4ヶ月健診は赤ちゃんの成長を確認する大切な機会です。
首のすわりや反応など「発達のチェック」が大きなポイント。
気になることは健診の場で相談してOK。
気になるサインがあれば、健診を待たずに受診するのも安心です。
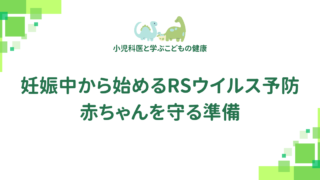
あとがき
赤ちゃんが少しずつ笑ったり反応したりする大切な時期です。
健診は「異常を探すだけ」ではなく、パパ・ママが安心できる場でもあります。
気軽に相談しながら、赤ちゃんの成長を一緒に見守っていきましょう。
最後までお読みいただきありがとうございます。
このブログでは「こどもの病気や健康」に関する正しい情報を小児科医の視点からお届けしています。
他の記事もぜひチェックして、日々の子育てにお役立てください。